
ハリスケース作り(1029回)
2023年2月17日(金曜日)
へら浮子作りで手間がかかるのは、一番最初に行う寸法等の生地合わせと竹足作りです。
カーボンが多く普及してる昨今ですが竹足はへら浮子にとってなくてはならない存在であります。その竹足は多くのへら浮子制作者は業者から仕入れてるのが現状です。
随分と昔になりますが私が浮子制作に関わるようになった当初はやはり業者から購入したり大手ホームセンターで販売してる竹籤を手に入れていました。他に編み棒の0番が使えると知りあちこちの手芸屋に行ったものです。
しかしへら浮子に使える良いものはありませんでした。
業者のものは炒りすぎて見た目は良いのですが強度が全くありません。短い足の底浮子などなら何とかなるかもしれませんが、竹そのものに柔軟性がないので長さがあるものには不向きで合わせた瞬間に足が折れることが考えられます。
実際に経験したことを踏まえるとやはり答えは自分で竹藪に入ることでした。
数年に一度あらかじめ役所に許可を得て長良川の河川敷に行って採取してきます。それを10年ほど工房の日陰で自然乾燥させて使用します。現在使ってる竹足も10年前のもので順繰りに使っています。
竹足の使える部位は縦繊維の多い表皮に近いところで、内面に行くに従って繊維が少なく足としてはもろく全く使えません。ホームセンターで売ってるのがこの部分です。
10年乾燥させた竹を輪切りにして鉈で縦割りをします。その後小刀である程度注文浮子に合うサイズに削り仕上げはペーパーで整えます。
強度を出すのに火入れはしますが過度に入れると内面の繊維が焼けて飴色の見た目が良いが使えない足となる。この辺はどの程度火入れをしたら良いかは経験かもしれません。
昔のへら浮子は竹足が最もポピュラーなものでしたが現代は野釣りの浮子でもカーボンやグラスを使用することが多くなりました。作り手としては竹よりカーボンの方がありがたい。採って切ったり削ったりする手間が省けるからです。20本の竹足を一から削るのに1日かかるのもその理由です。
でもやっぱり竹足は魅力でカーボン他にない魅力と利点が満載してる。
そしてハンドメイドにこだわるのだから竹も自分で採取し加工するものだと思うし、伝統のあるへら釣りだからこそ、こだわらなければならないへら浮子と確信しています。
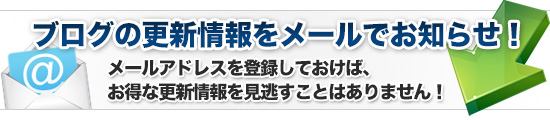
関連記事

ハリスケース作り(1029回)
2023年2月17日(金曜日)

竹足のこと(1028回)
2023年1月29日(日曜日)

今年一年の目標(1027回)
2023年1月16日(月曜日)

今年一年お世話になりました(1026回)
2022年12月31日(土曜日)

ヤフオク向けへら浮子(1025回)
2022年12月12日(月曜日)